万葉集の紫陽花、実はプロポーズの歌だった!?大伴家持の紫陽花の歌とは!?

💡 万葉集における紫陽花は、現代とは異なる意味を持っていた可能性がある
💡 大伴家持の「あじさい」の歌は、愛する女性へのプロポーズの歌である
💡 万葉集の時代背景から、家持と坂上大嬢の関係を探る
それでは、最初の章に入ります。
万葉集における紫陽花
万葉集における紫陽花の歌、とても興味深いですね。

✅ この記事は、万葉集にある大伴家持の「あじさい」の歌について、従来の解釈では「詐欺師に騙された」とされているが、それは誤解であり、実際には愛する女性へのプロポーズの歌であると解説しています。
✅ 歌の解釈は、漢字の本来の意味を理解することで、より正確な意味がわかることを示し、特に「諸苐等」は「弟」ではなく「新芽」を意味し、「練乃村戸二」は「村の戸から、最高に良いものを選びました」といった意味を持つことを説明しています。
✅ 記事は、歌の解釈を通して、言葉の持つ多様性と奥深さを示し、過去の言葉の解釈は、現代の解釈とは異なる可能性があり、新しい視点で捉え直すことの重要性を訴えています。
さらに読む ⇒ぜんこうのひとりごと出典/画像元: https://nezu3344.com/blog-entry-4938.html家持の心情が伝わってくる素敵な歌ですね。
万葉集には、紫陽花を詠んだ歌が2首のみ存在し、どちらも大伴家持の作品です。
1首目は、家持が恋心を抱く坂上大嬢から、恋人のように接する若い男性(諸弟)からの言葉を信じ、だまされてしまったことを歌っています。
2首目は、橘諸兄が紫陽花の八重咲きのように、長く愛する人を偲ぶことを歌っています。
当時の紫陽花は、現代のように人気のある花ではなく、万葉集における登場回数も少ないことから、当時の社会では縁起の良い花とはみなされていなかった可能性が考えられます。
万葉集の紫陽花の歌は、当時の社会における紫陽花の地位や、歌人たちの心情を垣間見ることができる貴重な資料と言えるでしょう。
家持さん、ロマンチストやなぁ。でも、現代でそんなプロポーズしたら、引かれへんかな?
家持と坂上大嬢の恋と時代の混乱
では、次の章に移りましょう。
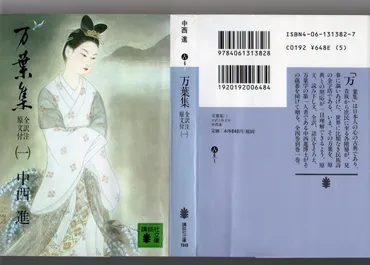
✅ この記事は、大伴家持の妻である「大嬢」についての歌とその解説、および小樽の厳しい冬の状況について記述しています。
✅ 歌の内容は、大嬢を「玉」にたとえ、常に一緒にいたいという家持の切実な気持ちを表現しています。
✅ 一方、小樽の冬は厳しく、積雪深は1mを越え、春の兆しはまだ感じられない状況が描写されています。
さらに読む ⇒万葉集の日記出典/画像元: https://souenn32.hatenablog.jp/entry/20180203/1517619150家持の切実な気持ちが伝わってきます。
家持が万葉集で詠んだ紫陽花の歌は、恭仁京にいた741年に坂上大嬢に贈った五首の連作の中で、不実な花として歌われています。
この歌は、当時の世相を反映しており、混乱と不安定な状況の中で、誰を信じていいのか分からず、心が晴れ晴れとしない家持の心情を表していると考えられます。
当時の貴族の男たちは、妻問婚という形式で複数の女性と関係を持つことが多く、女性は男の訪問を待つ立場にありました。
家持も坂上大嬢以外にも多くの女性と恋の歌を交わしていましたが、坂上大嬢とは特別な関係だったと考えられます。
大嬢も家持を愛していたのでしょうか?
混乱する時代と家持の不安定な立場
それでは、次の章に進みます。
公開日:2021/06/23

✅ 聖武天皇は、都の遷都を巡り、恭仁京、紫香楽宮、難波宮と迷走し、最終的に平城京に戻りました。その間、安積親王の急死や不審火、地震など、不穏な出来事が続きました。
✅ 聖武天皇の迷走は、藤原氏と橘氏の対立構造の中で、どちらにも寄りかかれず、苦悩する天皇の心情を表しており、家持も安積親王の死を悼み、世の無常を歌に詠みました。
✅ 聖武天皇は、藤原仲麻呂と橘諸兄を重用することでバランスを保ちながら治世を続けますが、最終的には藤原仲麻呂の勢力が強まり、孝謙天皇の政治の中心は藤原仲麻呂に移っていきます。橘諸兄は失脚し、家持は橘諸兄の死を悼む歌を詠んでいます。
さらに読む ⇒manabimon(まなびもん)出典/画像元: https://manabimon.com/ajisai-manyounohana-tatibanamoroe-to-yakamoti/混乱した時代の中での家持の心情が伝わってきます。
家持は当時、橘諸兄の庇護の下、内舎人として活躍していましたが、藤原広嗣の反乱や聖武天皇の迷走など、政治的な混乱に巻き込まれていました。
五首の中の「味狭藍」の歌は、諸弟らが誰を指すのか、解釈が難しいですが、家持を取り巻く状況が不安定であったことを示唆していると考えられます。
聖武天皇の迷走は、藤原氏と橘氏の勢力争いの影響が大きかったと考えられます。
紫陽花に重ねられた家持の心の状態
それでは、最後の章です。
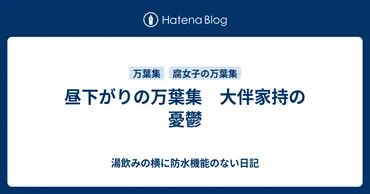
✅ 大伴家持が従妹である大伴坂上大嬢に贈った歌について、家持の心情と、忘れ草というモチーフについて解説している。
✅ 家持は過去に大伴坂上大嬢と深く結ばれていたが、何らかの理由で離れており、忘れ草を用いてその想いを断ち切ろうとするが、効果がないことを歌っている。
✅ 忘れ草は、中国の詩文集「文選」で憂いを忘れる効果があるとされ、その影響で恋に悩む貴公子たちが忘れ草を利用していたことが、家持の歌から窺える。
さらに読む ⇒湯飲みの横に防水機能のない日記出典/画像元: https://dakkimaru.hatenablog.com/entry/2020/10/29/005819忘れ草は、現代でも恋愛に悩む人にとって、切ないモチーフですね。
家持は坂上大嬢と離れて過ごすことが多く、心の苛立ちや不安定な状況の中で、紫陽花という花に不実なイメージを重ねて歌ったのかもしれません。
忘れ草、効かんかったんやなぁ。家持さん、つらいなぁ。
本日は、万葉集の紫陽花について解説しました。
💡 万葉集の時代、紫陽花は現代とは異なる意味を持っていた
💡 大伴家持の歌は、愛する女性へのプロポーズの歌であった
💡 万葉集の紫陽花の歌は、当時の社会状況と家持の心情を表している


