中国のゾウはなぜ旅をしたのか? 食料不足と「反食品浪費法」の真実習近平氏の食糧安全保障への強い意志とは!?
ゾウの旅からCOP15まで!中国の環境保護と食料安全保障の現状に迫る。豪雨被害、食糧自給率、食品浪費問題、そして「反食品浪費法」がもたらす影響とは?

💡 中国で生息地を離れて北上を続けていたアジアゾウの群れが、元の生息地へ戻りつつある
💡 中国では2021年4月29日、食品の浪費を禁止する「反食品浪費法」が可決された
💡 中国政府は、経済状況の悪化を受け、倹約を推進する方針を打ち出した
それでは、詳しく見ていきましょう。
ゾウの旅とCOP15:自然保護と気候変動の狭間
中国で象の旅が話題になった理由は?
自然保護への関心の高まり
ゾウの群れが元の生息地に戻りつつあるというニュースは、自然保護の成功を物語っているように感じますね。
公開日:2021/06/09

✅ 中国で生息地を離れて北上を続けていたアジアゾウの群れが、長旅を終え、元の生息地である雲南省シーサンパンナ(西双版納)タイ族自治州の自然保護区へ戻りつつある。
✅ ゾウの群れは、北上中、農地や村、都市などを通過し、当局はドローンや人員を投入して安全確保に努めてきた。
✅ ゾウがなぜ生息地を離れたのかは不明だが、経験の浅いリーダーによる道迷い、または新しい生息地探しが考えられている。
さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/57409711ゾウの群れが長旅を終え、無事に元の生息地に戻ることを願っています。
2021年、中国では16頭のアジアゾウの群れが雲南省を1年半かけて旅したニュースが話題となりました。
このニュースは、中国政府の自然保護に対するスタンスを垣間見ることができ、世界中から注目を集めました。
同年秋には、中国で初めてとなる国連の環境会議「生物多様性条約締約国会議(COP15)」がオンラインで開催され、中国の習近平国家主席はグリーンで低炭素な循環型経済の構築を強調しました。
しかし、中国は気候変動による影響も深刻化しており、2021年7月には河南省で観測史上最高の降水量を記録する豪雨が発生しました。
この豪雨は地下鉄浸水などの被害をもたらし、農作物にも甚大な被害がでています。
そうですね。中国政府は自然保護に力を入れていて、このゾウの群れの移動は、その取り組みの一例と言えるでしょう。
食料安全保障の危機:豪雨と「反食品浪費法」
中国は豪雨被害で食料安全保障にどう対応?
増産、輸入など多面的対策
なるほど。
豪雨による被害は深刻だったんですね。
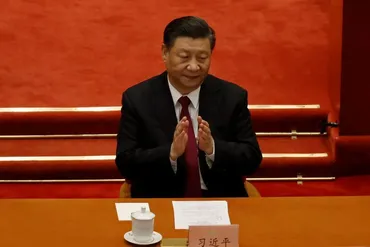
✅ 中国では2021年4月29日、食品の浪費を禁止する「反食品浪費法」が可決され、同時に施行されました。この法律により、大食い動画を投稿した場合は最高170万円の罰金、飲食店が客に過剰な注文をさせた場合は17万円の罰金が科せられる可能性があります。
✅ 中国では2013年から食べ残しを撲滅する「光盤運動」が始まり、2020年8月には習近平氏が「食べ物節約令」を発出しました。この指示は、唐の時代の詩を引用し、食料安全保障の危機感を訴えるものでした。
✅ 海外メディアは、中国の食料不足を懸念して報じましたが、北京大学は十分な食料があると反論しました。中国では、食べ残しに対する罰則として、奨学金の停止や罰金の徴収などが実施されています。また、レストランでは客の人数より少なく注文する「N-1ポリシー」やハーフポーションの提供、持ち帰り容器の提供などが導入されています。
さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/aee4077adfb3d7f02ef1423165955a2813f0c5c8「反食品浪費法」は、食料安全保障の観点から重要な法律だと思います。
中国政府は豪雨による農作物被害を受け、食料安全保障対策として、増産、食品ロスの削減、備蓄米の放出、海外からの緊急輸入など様々な対策を講じています。
しかし、中国の穀物自給率は近年低下傾向にあり、実際には95%を維持しているのか疑問視されています。
2021年4月29日、中国の全国人民代表大会(全人代)は食品の浪費を禁止する「反食品浪費法」を可決しました。
この法律は、習近平氏が2020年8月に出した指示を受け、2020年8月11日に発出された「食べ物節約令」に基づいています。
習近平氏は、食料安全保障の危機意識を訴え、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が警鐘を鳴らしたと述べました。
いや~、ホンマに、食料安全保障は大事やで!中国はホンマに、この問題には真剣に取り組んでるんやな。
食料浪費の抑制:光盤運動から「反食品浪費法」へ
中国の食品浪費削減対策、その背景は?
習近平氏の指示による
食料浪費が深刻化しているのは、世界共通の課題ですね。
公開日:2020/08/22

✅ 習近平国家主席は国民に対し、食糧浪費を減らすよう呼びかけ、食糧安全保障への危機意識を強調しました。
✅ 中国では、食糧浪費防止のため、抖音などの動画アプリで過食動画を投稿するアカウントを停止するなど、規制が強化されています。
✅ 食糧危機の背景には、長江流域の水害や農耕地の面積不足、米国への政治的な依存度が高まっている状況など、複数の要因が挙げられます。
さらに読む ⇒iza(イザ!)総合ニュースサイト:産経デジタル出典/画像元: https://www.iza.ne.jp/article/20200822-R5FYVPBG5NI2FNDPCFZS653N6U/中国政府は、食料浪費を抑制するために様々な対策を講じているんですね。
「反食品浪費法」は、食べ残しなどの食品浪費を禁止し、大食い動画の投稿や飲食店による過剰な注文を罰することによって、食品浪費を抑制することを目的としています。
中国では2013年1月、習近平氏の指示により、「光盤運動」が始まりました。
この運動は、当初は公務員の公金による宴会など、浪費を取り締まる意図がありましたが、その後、著名人や市民の間にも広がっていきました。
2020年8月には、習近平氏の指示を受け、食料を無駄にしないことについての国内の動きが始まりました。
大食い動画の禁止もその一つです。
この動きは、中国国営中央テレビや中国共産党機関紙「人民日報」で報道され、学校では食べ残しが多い生徒に対して奨学金申請の停止、食堂では食べ残しに対して罰金の徴収などが行われるようになりました。
私も、食べ物を無駄にするのはもったいないと思います。
倹約の推進:経済悪化と官僚機構の改革
中国政府は経済対策として何に取り組んでいますか?
倹約推進
中国の経済状況は厳しい状況にあるんですね。
公開日:2024/02/16
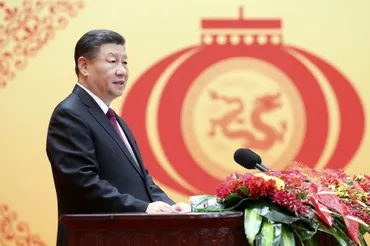
✅ 中国の1月の消費者物価指数が前年同月比0.8%下落し、デフレ懸念が高まっている。
✅ 歴史的にデフレは金本位制下で供給拡大が需要を上回った際に発生しやすく、大恐慌時には金本位制に固執した国ほどデフレが深刻化した。
✅ 日本は「失われた20年間」でデフレに陥ったが、これは官僚機構の強い権限とマクロ経済の専門知識不足、誤りを認めない姿勢が原因と考えられる。
さらに読む ⇒zakzak:夕刊フジ公式サイト出典/画像元: https://www.zakzak.co.jp/article/20240216-WRSUXLJOGVN4RCQDLG46APYLCM/官僚機構の改革は、容易ではないと思いますが、中国政府は真剣に取り組んでいるようですね。
中国政府は、経済状況の悪化を受けて、倹約を推進する方針を打ち出し、地方政府に対して「倹約を習慣とすべき」との指示を出しました。
これは、単なる一時的な措置ではなく、長期的な取り組みとして、官僚機構の無駄遣いを抑制し、地方政府の財政状況を改善することを目的としています。
具体的な対策としては、公的な式典やイベントの費用削減、会議のオンライン化、食べ残しの削減などが挙げられます。
地方政府は、これらの指示に従い、会議の規模縮小、ビデオ会議の活用、食品廃棄物の削減などを実施しています。
しかし、公務員の賃金が低く、人脈作りに豪華な贈答品が期待されるなど、構造的な問題も存在するため、支出削減は容易ではないと指摘されています。
中国も、デフレに悩んでるんやね。私も、デフレは経験済みやし、大変さは分かるわ。
食料廃棄の削減:世界的な潮流と中国の取り組み
中国が食品廃棄問題に立ち向かうため制定した法律は?
反食品浪費法
食料廃棄は、世界的に深刻な問題となっています。
公開日:2024/08/10

✅ 中国では、フードロスを減らすため、飲食店で注文可能な料理の量を制限する「反食品浪費法」が施行されました。この法律により、客は食べられる量以上の注文が禁じられ、大食い動画の制作・配信も禁止されます。
✅ 背景には、習近平国家主席が「フードロスは食料安全保障を脅かす問題」と述べたこと、そしてコロナ禍による食料供給チェーンの混乱があり、食料安全保障の重要性が認識されていることが挙げられます。
✅ 法律の施行により、飲食店は客に過剰な料理を注文させることが禁じられ、違反した場合には罰金が科せられます。しかし、個人客への罰則規定は不明確な点があり、飲食文化や自由への影響も懸念されています。
さらに読む ⇒VICE - VICE is the definitive guide to enlightening information.出典/画像元: https://www.vice.com/ja/article/china-bans-food-waste-mukbang/「反食品浪費法」は、食料廃棄削減に効果があることを期待したいですね。
中国では、年間1800万トンの食品が廃棄されており、これは年間で3000万人〜5000万人を養うことができる量に相当する。
そのため、2021年4月29日、「反食品浪費法」が可決され、食べ残しをした客に対して、飲食店側は食べ残した分の処分費用を請求できるようになった。
また、飲食店は客に適量を注文するよう促す必要があり、大量に注文させた場合は罰金が科される。
さらに、大食い映像の配信も禁止され、違反したテレビ局や動画配信業者にも罰金が科される。
この法律は、習近平国家主席が2020年8月に食べ物を浪費しないよう指示を出したことがきっかけとなった。
この動きは、地球資源が限界を迎える中、中国が文化を変えようとしていることを示している。
さらに、食糧安全保障への危機意識が高まっていることも、食品浪費が見直されている理由の一つである。
中国は、コメ、小麦、とうもろこしなど、主食については自給しているが、大豆などの農作物はアメリカからの輸入に頼っている。
新型コロナウイルスの感染拡大により、一部の農業大国で自国からの農産物輸出が制限されたことから、世界的に食料供給の不安定化が懸念されている。
日本でも、ファミリーマートでの食品寄付や廃棄食材を洋服の染料にするプロジェクトなど、食品ロス削減の取り組みが進んでいる。
今回の中国の「反食品浪費法」は、世界的に食料廃棄を減らす動きの中で、大きな一歩と言える。
今後、この法律がどのような効果を生むのか、注目が集まっている。
中国も、食料廃棄問題には本気で取り組んでますね!
中国の食料安全保障への取り組みは、世界にとって重要な課題です。
💡 中国では、アジアゾウの群れの移動や豪雨による農作物被害など、食料安全保障に影響を与える出来事が相次いでいる
💡 中国政府は、食料安全保障対策として、増産、食品ロスの削減、備蓄米の放出、海外からの緊急輸入などを実施している
💡 世界的に食料廃棄削減の動きが加速する中、中国の「反食品浪費法」は、その取り組みを加速させる可能性がある


