鷲田清一氏の哲学:多面的で温かい思想?とは!?
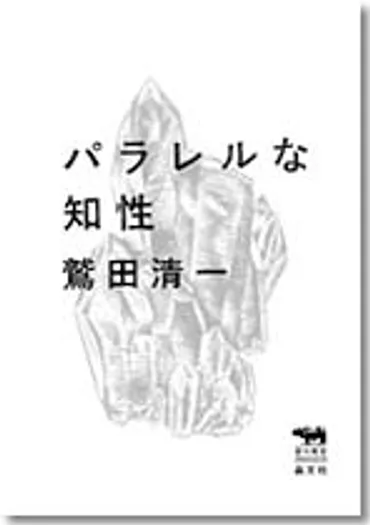
💡 鷲田清一氏は、臨床哲学や倫理学を専門とする哲学者です。
💡 氏の著作は、深い洞察と温かいまなざしで読者に共感と発見を与えます。
💡 現代社会における「待つ」ことの重要性を提唱しています。
それでは、鷲田清一氏の哲学について詳しく見ていきましょう。
鷲田清一氏の哲学:多面的で温かい思想
鷲田清一氏の哲学は、現代社会における様々な課題に対して、新たな視点を与えてくれます。
公開日:2021/03/19
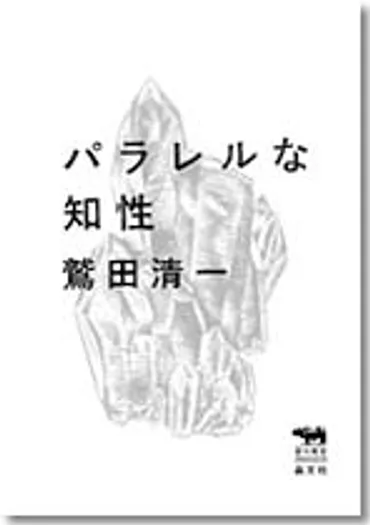
✅ 本書は、3.11以降、専門家に対する信頼が揺らいだ状況において、専門家と市民をつなぐ「パラレルな知性」の必要性を論じている。
✅ 著者は、科学者の倫理、大学の役割、コミュニティの課題、メディアの役割など、多角的な視点から「パラレルな知性」のあり方を考察している。
✅ 本書は、専門家と市民が共に考え、行動していくための指針を示す、現代社会における知性のあり方に関する哲学的考察である。
さらに読む ⇒晶文社出典/画像元: https://www.shobunsha.co.jp/?p=2902深い考察と温かいまなざしが印象的ですね。
鷲田清一氏は、臨床哲学や倫理学を専門とする哲学者で、医療、介護、教育の現場と哲学をつなぐ活動をしています。
彼の著作は、深い洞察と温かいまなざしで読者に共感と発見を与え、代表作には『「待つ」ということ』、『「ぐずぐず」の理由』、『パラレルな知性』などがあります。
『「待つ」ということ』は、現代社会における「待つ」ことの重要性を哲学的に考察した本で、待ち焦がれる時間、期待や願い、祈りなど、「待つ」という行為が持つ多面的な意味を分析しています。
『「ぐずぐず」の理由』では、擬態語を通して、人間の心情や言語表現の奥深さを探求し、オノマトペが持つ感覚的な抽象表現が、言葉の限界を超えて、人間の内面を豊かに表現する力を示しています。
『パラレルな知性』は、東日本大震災をきっかけに、専門家と社会の関係について提言した本で、専門知だけでなく、対話と共感による知性も必要であると主張し、現代社会における専門家の役割について深く考えさせてくれます。
そうですね。鷲田先生の言葉には、いつも心が温まります。
現代社会における「待つ」ことの重要性
現代社会において「待つこと」の重要性を改めて考えさせられました。
待ち時間の価値観について、改めて考えるきっかけになりました。
鷲田清一氏は、講演「待つことの意味」の中で、現代社会における「待てない日本人」の現状を指摘し、テレビのCMを待てない、待ち合わせ時間にイライラする、子どもを自分の期待通りに育てることに執着するなど、現代社会では「待つ」ことが非常に難しくなっている現状を嘆いています。
また、大学における中期計画・年度計画なども「待てない」風潮の一例として挙げ、短期的な成果にばかり目を向ける現状が、研究や教育の本来の目的を見失わせる恐れがあると警鐘を鳴らしています。
一方で、鷲田氏は「待つ」ことの真の意味は、「期待せずに待つ」「待たないで待つ」ことにあると強調し、「期待して待つ」ことは、むしろ視野狭窄に陥りやすいと指摘しています。
巌流島の決闘における佐々木小次郎の例を用い、「期待して待つ」ことによって、周りの世界に対して「武蔵が来る」という一点にしか目を向けられなくなる様子を描写し、待つことによって生まれる焦燥感や視野狭窄が、結果的に失敗を招くことを示唆しています。
このように、鷲田氏は現代社会における「待てない」風潮を批判し、「待つ」ことの真の意味を深く考察することで、より豊かな人生を送るためのヒントを与えています。
私も同感です。現代社会では、すぐに結果を求める風潮が強いですよね。
鷲田清一氏の経歴と主な著作
鷲田清一氏の経歴と主な著作について詳しくご紹介いただきありがとうございます。

✅ 1949年生まれの哲学者、せんだいメディアテーク館長、京都市立芸術大学学長であり、大阪大学総長も歴任した人物です。
✅ 京都大学文学部卒業、同大学院修了という経歴を持ち、哲学の視点から身体、他者、言葉、教育、アート、ケアなどを論じています。
✅ 社会・文化批評も行っており、著書に「モードの迷宮」「「聴く」ことの力」「しんがりの思想」「素手のふるまい」などがあります。
さらに読む ⇒art node出典/画像元: https://artnode.smt.jp/profile/20161121_287多岐にわたる活動と著作に、改めて敬意を表します。
鷲田清一氏は、哲学者であり、大阪大学総長を務めた人物(2011年8月25日まで)です。
1949年京都市生まれ、1972年に京都大学文学部哲学科を卒業、1977年に京都大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程を単位取得満期退学されています。
その後、関西大学、大阪大学で教鞭を執り、2007年から大阪大学総長に就任しました。
主な著書に『モードの迷宮』、『現象学の視線』、『ちぐはぐな身体』、『じぶん・この不思議な存在』、『だれのための仕事』などがあります。
鷲田先生は、様々な分野で活躍されていますね。
夕学講演会での講演内容
夕学講演会での講演内容について詳しくご紹介いただけますか。

✅ 藻谷浩介氏は、著書「デフレの正体」で、景気は人口構造の変化に影響されると主張しています。
✅ 本記事では、藻谷氏が全国調査で得たデータを基に、日本経済の虚像と実像を検証しています。
✅ 記事は、日本の経済状況について、一般的な認識とは異なる現実を示していることを強調しています。
さらに読む ⇒夕学(せきがく)講演会|慶應丸の内シティキャンパス定例講演会出典/画像元: https://www.sekigaku.net/sg/term/lecture/21講演内容が気になります!。
2011年7月22日には夕学講演会で「知的な体力について」をテーマに講演を行いました。
講演内容は知的な体力についてであり、夕学スタッフからは思索を深める3講演の一つとして紹介されています。
他の講演には、4/18(月)川島隆太氏「さらば脳ブーム」、7/1(金)田口佳史氏「見えないものを見る~東洋思想から読み解く日本文化と日本人~」、7/28(木)長岡健氏「アンラーニングが求められる時代~「大人の学び」の新たな展望~」があります。
知的な体力について、興味深い講演ですね。
鷲田清一氏の受賞歴
鷲田清一氏の受賞歴について教えてください。

✅ 関西弁が持つ奥深さや魅力について、標準語との対比を通して議論している。
✅ 鷲田清一さんと内田樹さんのトークが聴けるという情報と、彼らのプロフィールが紹介されている。
✅ 番組の内容や出演者、聴き方などの情報が記載されている。
さらに読む ⇒ ラジオデイズ出典/画像元: http://www.radiodays.jp/item_manager/show/2636数々の賞を受賞されているんですね!。
鷲田清一氏は、数々の賞を受賞しています。
主な受賞歴には、1989年のサントリー学芸賞(『分散する理性』『モードの迷宮』)、2000年の第3回桑原武夫学芸賞(『「聴く」ことの力』)、2004年の紫綬褒章などがあります。
素晴らしいですね。
本日は、鷲田清一氏の哲学についてご紹介しました。
💡 現代社会における「待つ」ことの重要性を再認識しました。
💡 鷲田清一氏の深い洞察と温かいまなざし、そして多岐にわたる活動に感銘を受けました。
💡 氏の哲学は、現代社会を生きる私たちにとって、貴重な指針となるでしょう。


