「オノマトペ」が導く言語の深淵!? 子供の言葉は大人を驚かせる!言語発達の謎を解き明かす!!
「ゲラゲラ」「モグモグ」身近なオノマトペが、実は言語の進化を解き明かす鍵?!幼児の言語習得から人間の思考まで、オノマトペを通して言語の本質に迫る!
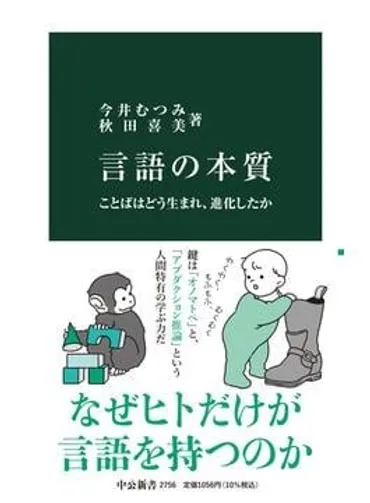
💡 幼児の言語習得において、オノマトペが重要な役割を果たす可能性を示唆
💡 オノマトペは、言語の身体性を示す重要な証拠となる
💡 オノマトペ研究は、言語の本質を探る新たな視点を与える
それでは、最初の章へ進んでいきましょう。
オノマトペと言語発達
オノマトペは言語発達にどう影響する?
重要な役割を果たす
なるほど、オノマトペと言語発達、興味深いですね。
公開日:2023/07/08
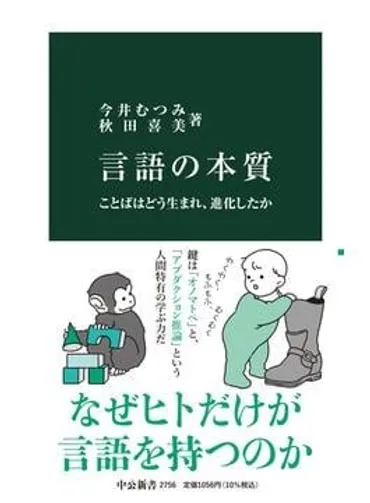
✅ 「言語の本質」は、オノマトペに着目し、言語の身体性、特に欧米中心の言語学への挑戦を提起する。
✅ 「サラサラ」などのオノマトペは、言語理解の足がかりとなり、言語の身体性を示す証拠となる。
✅ オノマトペから抽象的な概念への飛躍を可能にするのは、間違えることを許容するアブダクションという推論の力であり、これが言語習得や科学発展を促進すると論じられる。
さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/14951207オノマトペを通して、言語の身体性という側面が見えてくるのは、非常に興味深いですね。
今井むつみ先生は、著書『言語はこうして生まれる』でオノマトペが言語発達の重要な役割を果たすという仮説を提唱しています。
対談では、オノマトペが音象徴と呼ばれるように、音自体が意味を連想させるという点に注目し、様々な言語における「切る」という単語の例として、「k」や「t」といった音が共通して見られることを挙げ、音と意味のつながりを示唆しました。
さらに、オノマトペを使った動詞を学習した子供は、そうでない子供に比べて、動作を正しく理解できる割合が高かったという実験結果を紹介し、オノマトペが言語の初期段階において重要な役割を果たしたという仮説を裏付けました。
また、オノマトペは、その身体的な性質ゆえに、母語以外では理解しづらいという点も指摘されました。
全盲の作家、モハメド・オマル・アブディン氏が日本語を完璧にマスターしているにもかかわらず、オノマトペが苦手であるという事例を挙げ、オノマトペ習得には臨界期がある可能性を示唆しました。
幼少期に海外で育った人でも、両親が日本語を話していた場合は日本語に問題ないことが多い一方で、オノマトペだけは苦手という人が多いという経験から、「オノマトペ臨界期説」を提唱しています。
ええ、まさにその通りですね!オノマトペは、人間の身体と密接に結びついた言語表現であり、言語習得において重要な役割を果たしていると言えるでしょう。
言語の本質を探る、オノマトペの役割
オノマトペは言語習得にどんな役割を果たしている?
言語のミニワールド、大局観を教える
言語の本質について、新たな視点が提示されたんですね。

✅ 「言語の恣意性」という、言語記号の音声と意味の結びつきは社会慣習的な約束事であるという従来の考え方に対して、幼児の言語習得においてオノマトペが重要な役割を果たすという、身体性に基づいた新たな視点が提示された。
✅ オノマトペのような音と意味のつながりが感覚的に理解できる言葉は、身体性が言語習得に重要な役割を果たしていることを示唆し、言語学における「言語の恣意性」という概念を再考する必要性を提起している。
✅ 本書の議論は、ソシュール以降の文化・社会理論における「言語の恣意性」の考え方に影響を与え、人間の文化的営みにおける身体性の重要性を認識し直す必要があることを示唆している。
さらに読む ⇒中央公論.jp出典/画像元: https://chuokoron.jp/culture/124018.html従来の「言語の恣意性」とは異なる、興味深い視点ですね。
『言語の本質』は、オノマトペ研究の第一人者である秋田喜美先生と、認知言語学者の今井むつみ先生による共著で、オノマトペという身近な現象から言語の本質に迫る一冊です。
幼児が好むオノマトペに着目し、オノマトペが言語のミニワールドであり、子どもに言語の大局観を教える役割を果たしていることを明らかにします。
さらに、ヘレン・ケラーの言語習得の事例を挙げ、アブダクション推論という能力が、モノの名前と音の対応付けを可能にし、言語習得の基礎を築くことを示します。
本書は、オノマトペ研究とアブダクション推論という二つの手法を組み合わせることで、言語と身体、そして知覚の深い関係性を解き明かし、人間がなぜ言葉を持つのか、言語の進化とは何かという根源的な問いへと読者を誘います。
オノマトペという身近な現象を通して、言語の本質に迫る知的探求の旅へ、本書は読者をいざないます。
ホンマにそうやねん!オノマトペって、子供の言葉遊びみたいやけど、言語の本質を理解する上で大切な要素なんやな。
オノマトペと言語の二重構造
幼児の言葉習得でオノマトペが重要なのはなぜ?
身体感覚と意味が結びつくから
言語の二重構造という概念、初めて聞きました。
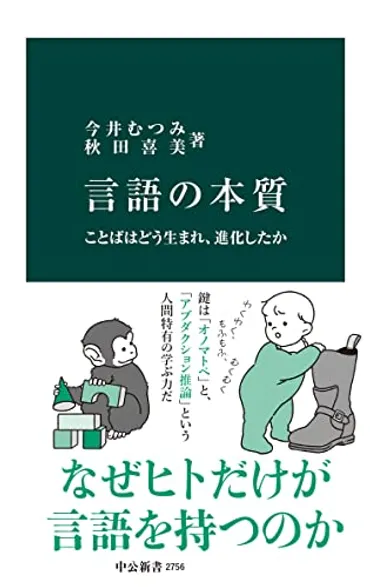
✅ 「オノマトペ言語起源説」を提唱し、言葉は感覚的な模倣から始まり、オノマトペが文法化され体系化されて現在の言語に進化したという仮説を立てています。
✅ 記号接地問題に対する解決策として、オノマトペが言葉の学習における重要な役割を果たし、そこからブートストラッピング・サイクルによって知識が積み上げられていくことを説明しています。
✅ 人間はアプダクション推論という非論理的な推論を行い、それが言語習得や科学の発展に貢献すると同時に、誤りや偏見を生み出す可能性も孕んでいることを指摘しています。
さらに読む ⇒mmpoloの日記出典/画像元: https://mmpolo.hatenadiary.com/entry/2023/07/15/193800言語の進化について、オノマトペという視点から考えるのは新鮮ですね。
今井むつみ氏、秋田喜美氏、千葉雅也氏の鼎談では、言語の本質を探る議論が展開されました。
特に、幼児の言語習得におけるオノマトペの効果に着目し、ソシュールが提唱した「言語の恣意性」という概念に疑問を呈しました。
ソシュールの記号学では、音声と意味の結びつきは社会慣習的な約束事であるとされていますが、オノマトペのように身体感覚的に結びつく言葉の存在は、この概念に対する新たな視点を与えます。
今井氏は、保育現場での経験から、オノマトペが幼児にとって効果的なコミュニケーションツールであることを指摘し、身体性と意味の結びつきが言語習得に重要な役割を果たしている可能性を示唆しました。
秋田氏は、オノマトペ研究者として、言語学において周辺的存在とされてきたオノマトペが、実は言語の根源的な部分に深く関わっているのではないかと考えています。
千葉氏は、哲学の観点から、言語の二重構造、つまりオノマトペ的な身体性の上に記号の恣意性が乗っかるという構造の存在を指摘し、ソシュール以降の文化・社会理論における言語の捉え直しが必要になる可能性を提起しました。
この鼎談は、言語の本質を探求する上で、従来の概念にとらわれず、新たな視点を取り入れることの重要性を示しています。
オノマトペという具体的な例を通して、言語と身体、文化、社会の関係について深く考察する内容となっています。
わあ、すごい!オノマトペって、言葉の起源に関わってるなんて、考えたこともなかったです。
言語の本質を探求する新書
オノマトペは言語の進化にどう関係している?
言語の起源と深く関係している
言語の起源と進化について、深く考察した内容ですね。
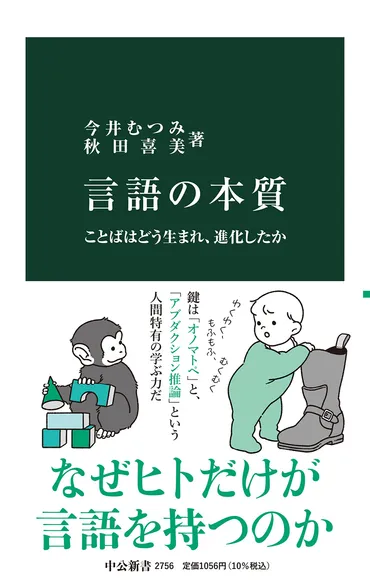
✅ 本書は、言語学と認知科学の専門家である著者2人が、言語の起源と進化、そして人間の本質について考察したものです。
✅ 言語の誕生と進化を紐解く鍵として、オノマトペとアブダクション(仮説形成)推論という人間の学習能力に着目し、ヒトが他の生物とは異なる言語能力を獲得したプロセスを探っています。
✅ 言語は単なるコミュニケーションツールではなく、知性や芸術、文化の基盤であり、人間存在そのものを理解するための重要な要素であることを示唆しています。
さらに読む ⇒中央公論新社出典/画像元: https://www.chuko.co.jp/shinsho/2023/05/102756.htmlオノマトペとアブダクション推論という、ユニークな視点から言語の本質に迫る内容ですね。
『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』は、認知科学者の今井むつみと言語学者の秋田喜美による共著で、オノマトペをキーワードに「言語の本質とは何か」を探求する新書です。
今井は、乳幼児の言語発達研究を通して、オノマトペが言語習得に重要な役割を果たすことに着目。
一方、秋田は、オノマトペが周辺的なテーマとされてきた言語学において、その言語現象としての側面に注目してきました。
本書では、2人の専門分野を融合させ、オノマトペを通して、言語の起源や進化、そして人間の思考やコミュニケーションとの関係を探ります。
従来の言語学とは異なる新しい視点から、言語の本質に迫る内容となっています。
なるほど、オノマトペとアブダクション推論、この組み合わせで言語の進化を解き明かすとは、斬新な発想ですね。
オノマトペが導く深遠な問い
「げらげら」「もぐもぐ」は、どんな秘密を隠している?
言語習得と進化の謎
オノマトペが言語の起源であるという主張は、興味深いですね。
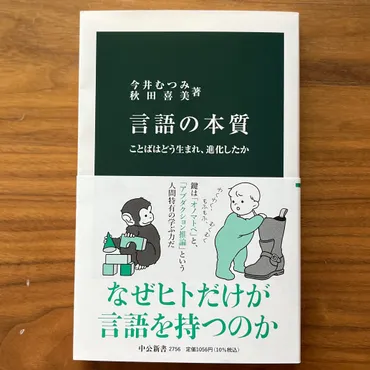
✅ 「言語の本質」はオノマトペが言語の起源であるという主張を展開し、言語学における従来の構文論中心の考え方への疑問を投げかける。
✅ 本書は、言語の構造ではなく、子供が言葉を習得するプロセスこそが本質であり、オノマトペはその典型例であると主張する。
✅ オノマトペがどのように抽象的な言語構造へと発達していくのか、そしてなぜ共通言語となるのかといった問題を提起し、言語学の世界に新しい視点を提供する。
さらに読む ⇒LISTEN出典/画像元: https://listen.style/p/books/9xtfr5yeオノマトペを通して、言語の深遠な問いが投げかけられるのは、とても刺激的ですね。
「げらげら」「もぐもぐ」といった日常的なオノマトペを題材に、子供たちの言語習得、言語進化の歴史、さらに人間がどのように世界を認識し、表現しているのかといった深遠な問いを投げかけます。
学術的な内容でありながら、わかりやすく読みやすい文章で書かれており、知的好奇心を刺激する一冊です。
オノマトペって、ホンマに深いんやな。言葉の起源とか、人間の思考とか、考えさせられるわ。
本日は、オノマトペと言語の関係について、興味深いお話をお伺いしました。
💡 オノマトペが、幼児の言語習得に重要な役割を果たす可能性がある
💡 オノマトペは、言語の身体性という新たな視点を与える
💡 オノマトペを通して、言語の本質を探る新たな道が開かれる


