幼児期の非認知能力を育む!CEDEPの取り組みとは?幼児教育の未来を拓く!
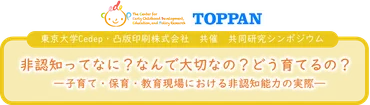
💡 CEDEP(東京大学大学院教育学研究科発達保育学実践政策学センター)は、幼児教育の質向上を目指した研究や実践を行っています。
💡 CEDEPは、保育現場と連携し、幼児期の非認知能力を育むためのアプリ開発や、園庭を活用した保育の質向上のための研究を進めています。
💡 地域環境を活用した保育の事例や、保育現場との連携について詳しくご紹介します。
それでは、最初のテーマに移ります。
幼児期の非認知能力を育むための共同研究とアプリ開発
幼児期の非認知能力は、社会性を育む上で非常に重要な要素ですね。
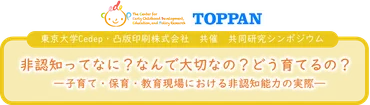
✅ 凸版印刷と東京大学Cedepは、幼児期の非認知能力を育むための共同研究「幼児期の非認知能力の育ちを支えるプロジェクト」を進めている。
✅ 本プロジェクトでは、保育現場で保育者が子供の非認知能力を「見とり・支える」ためのプログラム開発と効果検証を行っており、保護者や保育者の意識調査、タブレット用記録アプリの開発などに取り組んでいる。
✅ 2021年2月16日には、本プロジェクトの概要や調査結果、静岡県袋井市における実証実験などを紹介するオンラインシンポジウムが開催される。
さらに読む ⇒ 凸版印刷出典/画像元: https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2021/02/newsrelease210204.html保育現場で、保育者が子供の非認知能力を「見とり・支える」ためのプログラム開発を行うのは、画期的な取り組みですね。
CEDEPと凸版印刷株式会社は、幼児期の非認知能力の育ちを支えるための共同研究を実施しています。
この研究では、子どもの自発的な発信を記録するタブレット用アプリ「あのねぽすと」を開発し、保育における活用方法を実証実験しています。
このアプリは、子どもの発達過程を記録し、保育者の省察を助けることを目的としています。
研究チームは、アプリの開発に加え、非認知能力に関するコラムや学習アニメ動画を制作し、保育者向けに情報を提供しています。
また、共同研究シンポジウムを開催し、非認知能力の重要性やICT活用について議論しています。
これらの活動を通して、幼児期の非認知能力を育むための環境整備を目指しています。
ええ、このプロジェクトは、幼児期の非認知能力を育むための、非常に重要な取り組みだと思います。
園庭と地域環境を活用した保育の質向上
園庭は、子どもたちの遊びや学びにとって、非常に大切な場所ですね。

✅ 東京大学大学院教育学研究科発達保育学実践政策学センター 園庭調査研究グループは、2016年から、全国の保育・幼児教育施設の協力を得て、園庭や地域環境での保育・教育に関する調査研究、リーフレット作成、研修などを行っています。
✅ 同グループは、「園庭を豊かな育ちの場に:質向上のためのヒントと事例」や「森と自然を活用した保育・幼児教育ガイドブック」といった書籍を出版し、園庭での保育・教育の質向上のための視点や工夫、面積が小さな園や制約のある園での工夫、地域活用の工夫などを紹介しています。
✅ 石田佳織氏は、これらの書籍の執筆に加え、「保育内容 環境 第3版」の自然環境と持続可能な社会に関する章を担当し、園庭に関する専門知識を活かして、保育現場の質向上に貢献しています。
さらに読む ⇒園庭研究所出典/画像元: https://enteiken.com/about/園庭調査研究グループの取り組みは、保育現場にとって、大変参考になると思います。
CEDEP(園庭・地域環境での保育/子どもの遊び観研究プロジェクト)は、全国の保育・幼児教育施設と協力し、園庭や地域環境での保育・幼児教育、子どもの遊び観に関する研究を進めています。
調査研究、ブックレット作成、研修などを通して、保育の質向上を目指しています。
具体的な取り組みとして、園庭ブックレットの配布や、園庭での保育の質向上のための研修を提供しています。
そうやな、子どもたちの遊びは、まさに創造性を育む場やねん。
地域環境を活用した保育の事例紹介
地域環境を活用した保育は、子どもたちの学びを深める上で、非常に有効な方法だと思います。

✅ 東京都福生市で、東京大学大学院の幼児教育研究機関CEDEPと連携した保育・幼稚園における新たな教育手法を探る試験事業が行われています。
✅ 聖愛幼稚園では、園庭のオリーブの木を題材に、子どもたちの想像力や協調性を育むプログラムを実施しており、園児たちはオリーブの葉や枝を観察し、触ったり、絵を描いたりすることで、五感を使いながら学びを深めています。
✅ このプログラムでは、大人の介入を最小限に抑え、子どもたちの自主的な発見や探求を促すことで、主体的な学びを育むことを目指しています。
さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/290055聖愛幼稚園の取り組みは、子どもたちの想像力や協調性を育む、素晴らしい例ですね。
CEDEPは、地域環境を活用した保育の事例として、幼児と高齢者の交流や学び合いに取り組むオランダのTOYプロジェクトを紹介しています。
私も、地域の方々と連携して、子どもたちの学びを深めたいです。
保育現場との連携とフィードバック
デジタル時代においても、絵本や本の役割は、非常に重要ですね。

✅ ポプラ社と東京大学Cedepは、デジタルメディアの普及による「本離れ」の懸念から、子どもの読書環境改善を目的とした共同研究「子どもと絵本・本に関する研究」プロジェクトを開始しました。
✅ 本研究では、絵本・本の固有性や認知能力・非認知能力への影響、保育園・幼稚園における絵本環境などを科学的に調査し、デジタル時代における絵本・本の新たな価値発見を目指します。
✅ 研究成果を社会に発信することで、未来の子どもたちにより豊かな読書環境を提供し、読書推進活動の根拠となる科学的知見をアップデートすることを目指しています。
さらに読む ⇒ポプラ社出典/画像元: https://www.poplar.co.jp/topics/48312.htmlポプラ社とCEDEPの共同研究は、子どもたちの読書環境改善に大きく貢献すると思います。
CEDEPでは、保育現場からのフィードバックを重視し、現場と連携・連動したプロジェクトを展開しています。
ええ、デジタルネイティブ世代の子どもたちにも、絵本や本の魅力を伝え、読書の習慣を育むことが重要です。
CEDEPは、幼児教育の質向上に向けて、様々な取り組みを行っています。
💡 CEDEPは、幼児期の非認知能力の育ちを支えるための共同研究や、園庭を活用した保育の質向上に取り組んでいます。
💡 地域環境を活用した保育の事例や、保育現場との連携を重視し、実践的な研究を行っています。
💡 CEDEPの取り組みは、未来の子どもたちの教育に大きく貢献するでしょう。


