裁量労働制は本当に労働者を救うのか?裁量労働制改革とは!?
2023年4月、裁量労働制が厳格化!長時間労働問題に対処し、労働者の同意が必須に。働き方改革、あなたにとってのメリットと課題は?
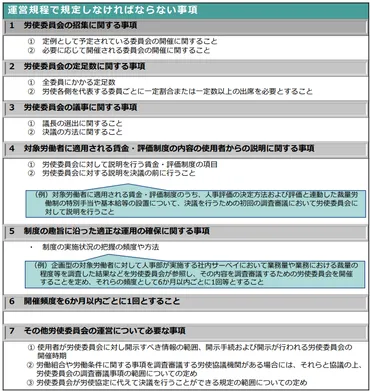
💡 裁量労働制の定義と改正点について解説します。
💡 裁量労働制の課題と問題点について詳しく掘り下げます。
💡 過労死防止対策と企業の責任について考察します。
それでは、最初の章に移ります。
裁量労働制改革:新たな課題と展望
裁量労働制、何が変わった?
労働者の同意が必須に
裁量労働制の対象業務が拡大されたことは、労働者の裁量権拡大と捉えることもできますね。
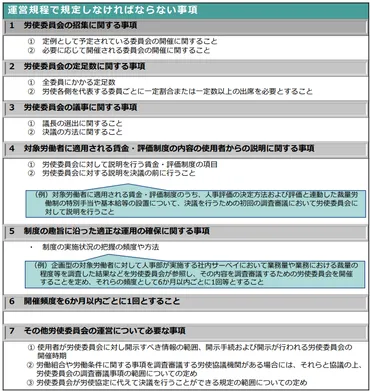
✅ 2024年4月施行の裁量労働制改正では、専門業務型裁量労働制の対象業務に「銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(M&Aアドバイザリー業務)」が追加されました。
✅ 改正により、対象業務は従来の19種類から20種類に拡大しました。ただし、M&Aアドバイザリー業務については、対象労働者が「調査または分析」と「考案および助言」の両方の業務に従事している必要があり、チームで分業している場合は対象外となります。
✅ 今回の改正では、対象業務の拡大に加えて、労働時間管理の強化、労働者の同意に関する規定の明確化など、労働者保護の観点からの改正も行われています。
さらに読む ⇒働く明日を、かんがえる 社内規程の総合メディア出典/画像元: https://www.kitelab.jp/column/2024-law-amendment/labor_system_change/今回の改正は、労働者保護の観点から重要な一歩と言えるでしょう。
2023年4月からの労働基準法施行規則改正により、裁量労働制の適用条件が厳格化され、労働者の同意が必須となりました。
これは、過去に裁量労働制が長時間労働や不当な運用に繋がっていた問題に対処するためです。
改正により、労働者は裁量労働制を拒否または撤回できるようになり、企業は労働者への選択肢を明確にしなければなりません。
一方で、適切な裁量労働制は、労働者に柔軟な働き方を提供する可能性も秘めています。
今回の改正は、裁量労働制の運用実態を見直し、労働者の権利と適切な働き方を保障するための重要なステップとなります。
しかし、実務レベルでは運用が難しい面も残っており、今後の労働者と企業の双方における理解と意識改革が求められます。
さらに、裁量労働制の適用をめぐる労働紛争は今後も増加する可能性があり、労働組合などの支援が必要となります。
そうですね、裁量労働制は労働者の能力や専門性を活かす有効な制度ですが、同時に労働時間管理や労働者の負担増加といった課題も抱えています。
裁量労働制の課題:長時間労働と過労死・過労うつ
裁量労働制は、本来の目的とは裏腹に、どんな問題を抱えているの?
長時間労働の温床になっている
裁量労働制の悪用によって、長時間労働が蔓延している現状は深刻ですね。
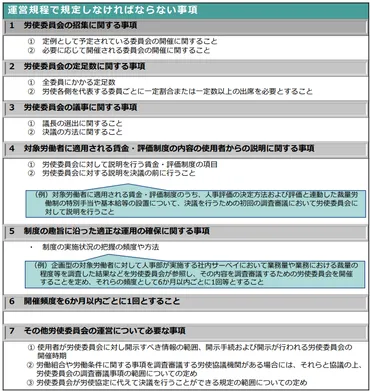
✅ 日本労働弁護団が裁量労働制の労働者に行ったアンケート結果によると、約2割の人が1日の平均労働時間を12時間以上と回答し、過労死ラインに達する水準であることが明らかになった。
✅ 調査では、裁量労働制の趣旨を逸脱し、出退勤時間を決められない人が24.4%いることも判明しており、長時間労働や裁量のない人が一定数いる実態が明らかになった。
✅ 国の審議会では裁量労働制の対象業種を広げる議論が進んでいるが、調査担当者は、このような実態がある中で拡大は危険だと訴えている。
さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/221738裁量労働制が過労死や過労うつを引き起こす可能性を示す、衝撃的なデータですね。
裁量労働制は、労働時間にかかわらず、みなし労働時間分の給与しか支払われない制度です。
本来は、仕事が終われば早く帰れる制度ですが、実際には、長時間労働を強いる手段として悪用されるケースが多いです。
近年、裁量労働制を適用した職場での過労死や過労うつが相次いでおり、2017年から厚生労働省は、裁量労働制での過労による労災認定数を公表するようになりました。
具体的には、2013年に証券アナリストの男性が、毎日午前3時ごろに起床し、午前6時ごろに出社して顧客向けレポートを30本以上作成し、18時半ごろに退社するような長時間労働を強いられ、心疾患で亡くなりました。
また、2004年にはシステムエンジニアの男性が、金融機関向けの新規システム開発を担当し、1ヶ月の時間外労働が123時間に及ぶなど、過労による精神疾患を発症しました。
これらの事例は、裁量労働制が、労働者を長時間労働に追いやり、過労死や過労うつを促進する可能性を示しています。
さらに、裁量労働制では、労働時間が明確に把握されないため、過労死や過労うつを「自己責任」に転嫁しやすいという問題点もあります。
ホンマに、裁量労働制って、労働者の負担が増えてるんちゃうかな?
裁量労働制の悪用防止:労働時間管理の必要性
裁量労働制拡大で何が懸念?
過労死・うつ防止が課題
裁量労働制は労働者の自由度を高める一方で、管理不足に陥りやすいという側面もありますね。
公開日:2024/06/07
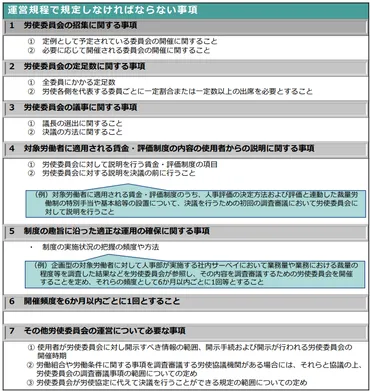
✅ 裁量労働制は、労働者の業務遂行手段や時間配分を委ねる制度だが、仕事の量や完成時期までを労働者に丸投げするものではない。使用者には、労働者の裁量の範囲で解決できない問題に対して対策を講じ、労働者の過重労働を防ぐ義務がある。
✅ 使用者には、裁量労働制においても労働者の健康・福祉確保の措置と苦情処理措置を講じる義務がある。具体的には、労働時間の状況把握、代償休日や特別休暇の付与、健康診断の実施、 相談窓口の設置、産業医による指導助言などが必要となる。
✅ 裁量労働制の運用においては、みなし労働時間と実労働時間の乖離が生じないように、労働時間の状況を把握し、労働者の健康状態を管理することが重要である。不適切な運用は、過労死や過労自殺といった深刻な事態につながる可能性も孕んでいるため、制度の趣旨と留意点を正しく理解し、適切な運用を行う必要がある。
さらに読む ⇒マネーフォワード クラウド - バックオフィスから経営を強くする出典/画像元: https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/127/労働時間管理は、労働者の健康を守る上で非常に大切です。
2018年の労働基準法改正案では、裁量労働制の拡大が議論されていますが、過労死や過労うつを防ぐためには、労働時間の上限規制と同時に、裁量労働制の悪用を防ぐ対策を講じる必要があります。
具体的には、労働時間の実態把握を徹底し、長時間労働を抑制する措置を講じることが重要です。
私も、裁量労働制って、ちゃんと管理しないと、大変なことになると思います。
過労死ラインの見直し:多角的な健康被害対策
過労死ライン見直しで何が変わった?
負荷要因考慮、認定基準強化
過労死ラインの改定は、労働者の健康を守るための重要な一歩ですね。
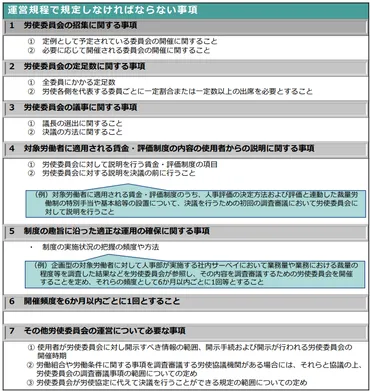
✅ 「過労死」の現状と定義、2021年の新基準、そして過労死防止対策について解説しています。
✅ 2020年の労災請求件数は減少したものの、依然として多く発生しており、過労死等の定義や、改正された労災認定基準について説明しています。
✅ 長時間労働は過労死の大きな要因であり、新基準では労働時間だけでなく、勤務間インターバルや身体的負荷なども考慮されるようになったことを説明し、過労死防止対策として長時間労働の削減を呼びかけています。
さらに読む ⇒産業医・産業保健のことなら|株式会社エムステージ出典/画像元: https://sangyoui-navi.jp/blog/338労働時間だけでなく、精神的なストレスや身体的負荷も考慮することで、より適切な過労死防止対策となるのではないでしょうか。
2021年に過労死ラインが見直された背景には、働き方改革の進展と長時間労働による健康被害問題の顕在化があります。
20年ぶりの改定では、労災認定基準が総合的に見直され、労働時間だけでなく、労働時間以外の負荷要因も考慮されるようになりました。
具体的には、長期間の過重業務の評価において、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に評価することが明確化され、短期間の過重業務における労働時間以外の負荷要因の見直しが行われました。
また、業務と発症の関連性が強いと判断できる場合の明確化も図られ、脳・心臓疾患の対象疾病に「重篤な心不全」が追加されました。
今回の見直しにより、長時間労働だけでなく、業務上のストレスや負荷など、多角的な要因を考慮した労災認定が可能となり、従業員の健康を守るための取り組みがより重要になっています。
過労死ラインの見直しは、労働者の健康を守るためにも必要だと思います。
企業の責任:過労死・健康被害対策の強化
企業は従業員の健康を守るためにどんな対策が必要?
多岐にわたる対策が必要
過労死等防止対策白書の内容は、企業にとって重要な指針となるでしょう。
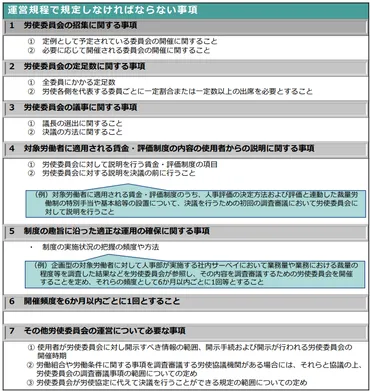
✅ 令和4年版 過労死等防止対策白書は、過労死等に関する現状と対策を網羅しており、労働時間、メンタルヘルス、自殺、労災補償、公務災害、疫学研究結果等を詳しく分析しています。
✅ 白書は、働き方改革が進んでいるものの、人手不足が深刻化しており、今後過重労働による健康障害や過労死の増加が懸念されることを示しています。
✅ 過労死等防止に向けた政府の施策として、労働行政機関による対策、調査研究、啓発、相談体制整備、民間団体への支援などが紹介されています。
さらに読む ⇒ 労務ドットコム出典/画像元: https://roumu.com/archives/113706.html企業には、従業員の健康を守るための責任が大きく、様々な対策が必要となります。
企業は、過労死や健康被害対策として、長時間労働の抑制、従業員へのストレス軽減のためのプログラム導入、メンタルヘルス対策の強化など、多岐にわたる対策を講じる必要があります。
企業は、従業員の健康と安全を最優先に考え、過労死や健康被害を防ぐため、積極的に対策を講じるべきです。
今回の記事では、裁量労働制の現状と課題、そして過労死防止対策について解説しました。
💡 裁量労働制は、労働者の負担増加や過労死などのリスクを孕んでいます。
💡 過労死防止対策として、労働時間管理の徹底や企業の責任強化が重要です。
💡 労働者の健康を守るため、適切な制度設計と運用が必要です。


