元興寺の鬼は本当にいる?奈良の伝説と歴史を紐解く元興寺の鬼とは!?

💡 元興寺には鬼の伝説が数多く存在する
💡 境内には鬼の置物が設置され、参詣者を魅了する
💡 元興寺は、鬼を内包し、大切に扱う独自の文化を持つ
それでは、最初の章、元興寺の鬼について詳しく見ていきましょう。
元興寺の鬼
元興寺は歴史的な場所であり、鬼の伝説は多くの人々を魅了する要素の一つですね。
公開日:2017/09/12

✅ 元興寺境内には、鬼の置物が5体設置されており、鬼探しを楽しむことができます。鬼は境内だけでなく、元興寺周辺の地名や伝説にも登場し、奈良の歴史と密接に関わっていることがわかります。
✅ 元興寺の節分では、「鬼は外」ではなく「鬼は内」と唱えます。これは、鬼を悪の存在ではなく、祖先や神聖な存在として敬う思想に基づいていることを示しています。
✅ 元興寺小子坊の裏庭には、仰向く鬼の置物が設置されています。小子坊は、かつて北厨房として機能していた建物で、現在も県指定文化財として保存されています。小子坊内には、不動尊護摩供養が行われており、歴史を感じることができます。
さらに読む ⇒奈良の宿大正楼出典/画像元: https://narayado.info/nara/gagoze-syoshibo.htmlなるほど、元興寺は鬼を悪の存在としてではなく、神聖な存在として捉えているんですね。
とても興味深いです。
奈良県にある元興寺は、鬼にまつわる伝説が残る場所として知られています。
境内には、5体の鬼の置物がひっそりと置かれ、参詣者に楽しませています。
特に小子坊の裏庭にいる鬼は、女性らしい悩ましい姿態で印象に残る存在です。
元興寺では節分会で「鬼は内」と唱え、鬼を内包し大切にするという独特な文化があります。
鬼は、昔話では雷の申し子である大力の童子によって退治された悪霊の変化とされています。
童子は鬼を退治した功績から八雷神、元興神と称えられ、元興寺と深く関わっています。
小子坊はかつて北厨房として使われていた建物で、裏庭には鬼の置物があります。
また、小子坊内では毎月28日に不動尊護摩が行われています。
ホンマに?元興寺の鬼、ちょっと怖いけど、興味あるわ!
奈良妖怪新聞が語る元興寺
それでは、次の章に移りましょう。
奈良妖怪新聞が語る元興寺についてです。

✅ 「奈良妖怪新聞」が100号を迎え、これまでに取り上げた妖怪の中から特に興味深いものを5つ紹介。
✅ 酒呑童子の幼少期が奈良の白毫寺にいたという伝説や、元興寺のオニの伝説を紹介。
✅ 記事では、これらの伝説がどのように現代に受け継がれているのか、また、歴史的な背景や解釈について考察している。
さらに読む ⇒webムー 世界の謎と不思議のニュース&考察コラム出典/画像元: https://web-mu.jp/history/42367/奈良妖怪新聞、面白いですね!元興寺の鬼に関する記事も載っているんですね。
『奈良妖怪新聞』は、奈良県に伝わる妖怪伝説や「オバケ譚」を毎月ひとつずつ紹介している月刊新聞で、2024年7月に100号刊行を達成しました。
今回は、100号記念として、これまで取り上げた内容の中から、特に印象深いものを5つ紹介しています。
その中には、定番中の定番である「オニ」について、酒呑童子の奈良でのエピソードや、元興寺のオニについて解説した内容も含まれています。
酒呑童子は、京の都が舞台として有名ですが、奈良にも生息していたというエピソードがあり、白毫寺にいたという伝説が残っています。
元興寺のオニは、『日本霊異記』に由来しており、夜な夜な鐘堂に出没し人に危害を加えていたとされています。
その後、道場法師によって退治され、その血の跡をたどると「不審ヶ辻子」に至るという話が残っています。
しかし、現在の元興寺は平城京の元興寺でなく、本元興寺(飛鳥寺)のことであるため、『霊異記』と現在巷で聞かれる元興寺のオニとはイコールではない可能性も指摘されています。
奈良妖怪新聞、私も読んでみたいです。元興寺の鬼の伝説についてもっと知りたいです。
元興寺の伝説
続いて、元興寺の伝説についてお話しましょう。
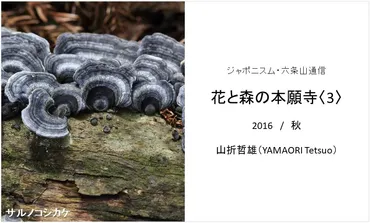
✅ 大谷光演の句「勿体なや祖師は紙衣の九十年」は、親鸞の質素な生活と現代人の贅沢な生活を対比し、無駄を省き、敬意を持って生きることの重要性を訴えている。
✅ ケニアのワンガリ・マータイは、この句から「モッタイナイ」という言葉を発見し、環境問題解決のための3R(リデュース、リユース、リサイクル)を提唱し、世界に広めた。
✅ マータイは後に「モッタイナイ」には4つ目のRである「リスペクト(尊敬)」が必要であると提唱し、著者は彼女との対談でその考えを確認した。
さらに読む ⇒ジャポニスム振興会|誇り高き日本人づくりをめざして出典/画像元: https://japonisme.or.jp/rokujoyama-note/hana-mori-3/元興寺の鬼の伝説は、神霊の秘匿性、つまり隠れ身を表すものとして注目されているんですね。
元興寺(がごぜ、がごじ、ぐわごぜ、がんごう、がんご)または元興寺の鬼(がんごうじのおに)は、飛鳥時代に奈良県の元興寺に現れたという妖怪です。
雷神が子供の姿に変身し、農夫の妻が怪力を持つ子供を産みます。
この子供は元興寺の童子となり、鐘楼の童子たちの変死事件を解決するために、夜中に現れた鬼と戦い、その髪の毛を引き剥がして退治しました。
この鬼は元興寺で働いていた下男の霊鬼であることが判明し、その髪の毛は元興寺の宝物となりました。
この童子はその後、怪力で活躍し、得度出家して道場法師になったとされています。
この話は、神霊の秘匿性(隠れ身)を表すものとして、山折哲雄によって注目されています。
また、お化けを意味する児童語のガゴゼやガゴジは、元興寺の伝説に由来するともされていますが、柳田國男はこれを否定し、化け物が「咬もうぞ」と言いながら現れることが起因するという説を唱えています。
元興寺の鬼の伝説は、古代の信仰や文化を垣間見ることができる貴重な物語ですね。
元興寺の歴史
それでは、最後の章、元興寺の歴史について触れていきましょう。

✅ 織田信秀は、尾張国の勝幡城を拠点とし、その後、清洲城、安祥城など、複数の城を居城として移し、その支配地を広げていきました。
✅ 信秀の居城移転は、嫡男である織田信長に大きな影響を与えたと考えられ、信長の城へのこだわりや戦略にも繋がるものと考えられています。
✅ 信秀は、今川氏との戦い、美濃国の土岐氏との戦いなど、数々の戦いを経験し、その過程で戦略的な居城の選択と移転を進めたことがわかります。
さらに読む ⇒城びと - お城を知って、巡って、つながるサイト出典/画像元: https://shirobito.jp/article/1338織田信秀と元興寺の関係は、なかなか興味深いですね。
元興寺は、尾張国阿育知郡片輪里(現・愛知県名古屋市中区古渡町付近)に存在していましたが、織田信秀によって移転され、現在も尾頭願興寺として存在しています。
信秀さん、元興寺を引っ越しさせたのは、何か理由があったんやろか?
元興寺の風景
では、最後に元興寺の風景についてお話しましょう。

✅ 世界遺産の元興寺では、桔梗、紫陽花、ハルシャギク、萩など、季節の花々が咲き乱れています。
✅ 特に境内南側の石仏の間にあるたくさんの桔梗が見頃を迎えており、心が洗われるような美しさです。
✅ 極楽堂・禅室の屋根には、日本最初の瓦である行基葺きが使用されており、歴史と文化に触れながら静かな時間を過ごせます。
さらに読む ⇒元興寺」の桔梗が見ごろです – ならまち情報サイト出典/画像元: https://naramachiinfo.jp/information/%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%BE%E3%81%A1%E7%95%8C%E9%9A%88%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/2879.html元興寺は、美しい花々も魅力の一つですね。
季節の花が咲き乱れる風景は、見ているだけで心が安らぎますね。
元興寺は、桔梗の名所としても知られており、境内には鐘楼跡礎石も残っています。
かつての元興寺は奈良町エリアを含めた広大な境内を誇っていたことがわかります。
元興寺は、歴史だけでなく、自然も豊かなんですね。いつか行ってみたいです。
元興寺は、鬼の伝説や歴史、そして美しい風景など、魅力あふれる場所です。
ぜひ実際に訪れて、その魅力を体感してみてください。
💡 元興寺は鬼の伝説と深い関わりを持つ
💡 奈良妖怪新聞では元興寺の鬼に関する記事が掲載されている
💡 元興寺の風景は、歴史と自然が調和した美しい空間


