大阪大学 論文不正問題を徹底解説!調査と再発防止策は?大阪大学産研における研究不正問題の全容
大阪大学で発覚した研究不正。データ改ざんにより論文2編が撤回、教授らに処分も。ずさんなデータ管理や記録不足が原因。大学は再発防止へガイドライン整備も、具体的な対策は不明。研究公正への取り組みと、今後の課題を問う。
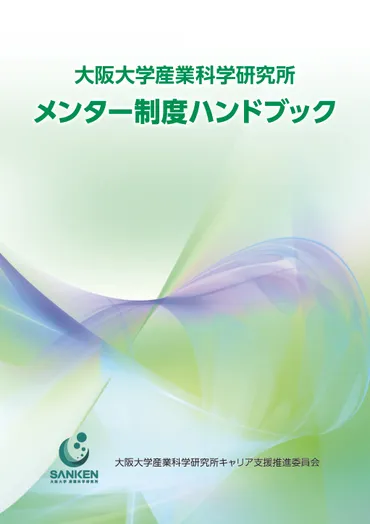
💡 大阪大学産業科学研究所で、論文の改ざんが発覚し調査委員会が設置された。
💡 2編の論文でデータ改ざんが認定され、関与者が不正行為者として認定された。
💡 大学は論文の取り下げ勧告と関係者の処分を行い、再発防止策を検討している。
今回の記事では、大阪大学産業科学研究所で起きた論文不正問題について、詳細に見ていきましょう。
まずは、問題の発端から、その後の調査、最終的な処分、そして再発防止に向けた大学の取り組みまでを解説します。
告発と調査の始まり
阪大で発覚した研究不正、一体何が問題だったの?
論文の改ざんという不正行為が発覚。
産研の概要から、不正行為の告発までの流れを追います。
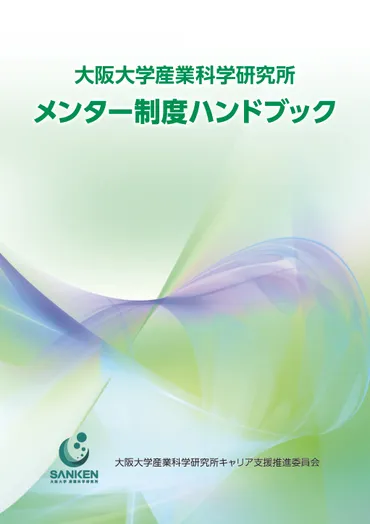
✅ 産研には、28の研究室があり、210名の大学院生が在籍している。
✅ 国内外の学生や社会人を対象とした活動を通して、科学への関心を高めている。
✅ 社会・地域への教育・研究・イノベーション拠点としての貢献を目指している。
さらに読む ⇒大阪大学産業科学研究所出典/画像元: https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/about/disclosure.html210名もの大学院生が在籍し、社会貢献も目指している産研で、このような不正行為が起きたことは、非常に残念です。
研究活動の信頼性を揺るがす事態ですね。
令和2年12月、大阪大学産業科学研究所において、教授、准教授、および元大学院生による研究活動上の不正行為(改ざん)が告発されました。
事態を重く見た大学は調査委員会を設置し、4編の論文を調査対象としました。
これは、研究活動の信頼性を揺るがす重大な事態として、大学全体に衝撃を与えました。
今回の件は、研究活動の信頼を大きく損なうものであり、非常に遺憾です。大学として、徹底的な調査と再発防止策が求められるでしょう。
不正行為の内容と認定
論文改ざん!研究不正で誰が責任を問われた?
教授、准教授、元大学院生が不正行為者に。
不正行為の内容と認定について、詳しく見ていきましょう。
公開日:2016/02/02

✅ 岡山大学の医学論文について、実験画像の切り張りが確認されたにも関わらず、本来必要な生データとの照合をせずに「不正なし」と結論づけられていたことが判明しました。
✅ 調査報告書には切り張りや生データに関する記載がなく、別の論文でも画像説明との食い違いが見られたものの、問題視されませんでした。
✅ 研究不正に関する国のガイドラインに従い、調査結果は公表されていません。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20160103/k00/00e/040/086000c岡山大学の事例と今回の大阪大学の事例を比較すると、データ改ざんの手口や、調査の過程に共通点が見られます。
これは、研究不正がどの大学でも起こりうる問題であることを示唆していますね。
調査の結果、2編の論文において改ざんが認定されました。
2020年の論文においては、データ解析ソフトによる平滑化処理や手作業でのデータ変更が行われ、グラフの再現性も保証されない状態でした。
一方、2015年の論文では、論文に記載された解析手法では図が再現できず、准教授が異なる手法で再現実験を行ったものの、その記録も不十分でした。
これらの不正行為に関与したとして、教授、准教授、元大学院生が不正行為者として認定されました。
論文の責任著者である教授は、不正行為に直接関与していなかったものの、責任を負うこととなりました。
いやしかし、実験データの切り張りって…まるで手品みたいやな。何でこんなことしたんやろ?責任者の方々の今後の対応にも注目やね。
次のページを読む ⇒
論文不正で教授ら処分。大学は再調査せず。研究倫理の向上目指し、再発防止策の強化が課題。

