出産議員ネットワーク、女性議員の出産・育児支援とは? 院内集会や議会規則改正の動きを解説?女性議員の出産・育児支援、院内集会から議会規則改正まで
女性地方議員の出産・育児問題を解決!出産議員ネットワークが、議員の産休明文化や議会運営改善を実現。マニフェスト大賞受賞も!子育て議員連盟との連携、院内集会開催、そして女性政治参画への課題と展望を提示。未来を変える活動に注目!
議会規則改正と進展
女性議員の出産・育児、議会はどう変わった?
産休が明文化、周囲の理解が深まりました。
議会規則改正について、詳しく見ていきましょう。
公開日:2021/04/08
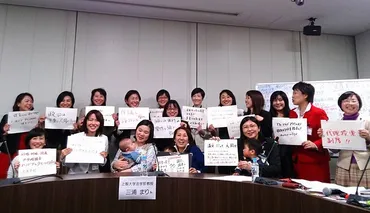
✅ 地方議会で女性議員が出産する際の産休を保障するため、標準会議規則が改正され、労働基準法と同等の産前6週、産後8週の産休が明記された。
✅ これまでは欠席理由として「出産」を認める形だったが、議会内の理解不足や本人の遠慮により十分に休めないケースがあったため、今回の改正となった。
✅ 今回の改正は、多様な人材の政治参加を促すための要請や男女共同参画基本計画に基づき行われ、出産議員ネットワークの活動も後押しとなった。育児に関する課題も指摘されている。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASP465V36P2LUTIL03Y.html議会規則の改正は、出産議員ネットワークの活動の大きな成果ですね。
今回の改正が、女性議員の方々の安心につながることを願います。
出産議員ネットワークの活動は、議会規則の改正という具体的な成果に繋がりました。
2021年の標準会議規則改正により、女性議員の産前産後休業が明文化され、労働基準法に準じた産前6週、産後8週の休業が認められるようになりました。
背景には、「第5次男女共同参画基本計画」があり、政治分野における女性の参画拡大に向けた取り組みが促されました。
総務省の調査では、改正後に出産、育児に関する明文規定が大幅に増加し、育児に関する規定の整備が進んでいます。
九州大学のインタビュー調査では、会議規程に「出産」が明記されたことで、周囲の理解が深まり、出産・育児が認められるようになったという事例が紹介されています。
すごい! 議会規則が変わると、周りの人も理解してくれるようになるんだね。私も将来、政治に関わることを考えているから、すごく勉強になるな。
政治分野における女性参画推進の取り組み
出産・育児世代の政治参画、何が重要?
両立支援と合理的配慮がカギ。
政治分野における女性参画推進の取り組みについて、見ていきましょう。
公開日:2021/12/12
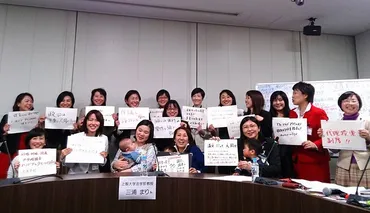
✅ 政策本位の政治を目指す「第16回マニフェスト大賞」で、出産・育児と議員活動の両立を目指す「出産議員ネットワーク・子育て議員連盟」がグランプリを受賞した。
✅ 同連盟は、全国の超党派議員約250人で構成され、現場の声に基づいた要望活動を行い、議会規則の改正や政治分野における男女共同参画推進法の改正に貢献した。
✅ 代表の永野裕子・東京都豊島区議は、多様な声を反映させた議会の重要性を語った。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20211112/k00/00m/040/256000c「政治分野における男女共同参画推進法」の施行と、今後の課題についても触れられていますね。
出産・育児世代の議員が増えることが、少子化対策にも繋がるというのは、とても重要な視点だと思います。
「政治分野における男女共同参画推進法」の施行に向けた動きと、その後の課題についても触れられています。
少子化や女性活躍の課題解決には、出産・育児世代の議員増加が重要であるという認識が共有されています。
2024年8月26日には、衆議院第二議員会館で「出産議員ネットワーク・子育て議員連盟院内集会」が開催され、「女性・子育て世代の政治参画をどう進めるか」をテーマに、議員活動と出産・子育ての両立支援、オンライン議会、統一地方選における課題などについて議論が行われました。
パネルディスカッションには、専門家や地方議員が参加し、出産議員に必要な合理的配慮の重要性が訴えられました。
今後の活動では、課題を体系的に整理し、各地方議会での環境整備を促すことを目標としています。
マニフェスト大賞の受賞、おめでとうございます。多様な声を反映させる議会という言葉が大変印象的でした。今後の活動に期待しています。
女性議員の増加に向けた課題と展望
なぜ政治の世界で女性の参画拡大は難しい?
家事・育児との両立、旧姓使用制限などが要因。
女性議員の増加に向けた課題と展望について、お話しします。
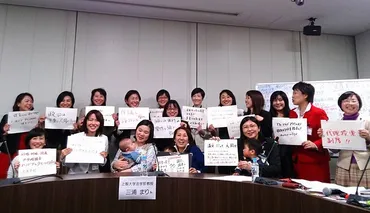
✅ 出産・育児を経験した女性地方議員らでつくる「出産議員ネットワーク」が、仕事と家庭を両立できる社会の実現に向けた議会の役割について集会を開いた。
✅ 集会では、議員の産休育休制度の必要性や、議会における性別役割分担意識が課題として挙げられ、党派や性別に関係なく行動で示す必要性が強調された。
✅ ネットワークの調査によると、在任中に出産した議員がいる議会は少数であり、具体的な議論を始める時期に来ていると認識されている。
さらに読む ⇒東京すくすく子育て世代がつながる―東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/1337/女性議員の増加は、まだまだ課題が多いのですね。
旧姓の使用制限など、初めて知ることも多く、驚きました。
出産議員ネットワークの今後の活動に期待しています。
政治分野における女性の参画拡大は、依然として多くの課題を抱えています。
衆院議員における女性比率は依然として低く、女性候補者の立候補を阻む要因として、家事・育児との両立の困難さ、プライバシーの懸念、旧姓の使用制限などが挙げられています。
超党派議連は、各政党に女性候補者数の目標設定を義務付ける法改正を目指しましたが、自民党内の理解が得られず、義務化は見送られました。
今後の展望としては、出産議員ネットワークの活動を通じて、出産・育児と議員活動の両立支援、そして、女性議員がより活躍できる環境整備が求められています。
女性議員の増加は、まだまだ課題が多いとのことですが、出産議員ネットワークの活動は、少しずつでも確実に、良い方向へ進んでいると思います!
女性議員の出産・育児に関する課題と、それに対する様々な取り組みについてご紹介しました。
今後の活動に期待します。
💡 出産議員ネットワークは、女性議員の出産・育児に関する課題解決を目指し、実態調査や議会規則改正など多岐にわたる活動を展開しています。
💡 地方議会では、女性議員の産休・育休に関する規定が未整備であり、議員の仕事と家庭の両立を阻む課題が浮き彫りになっています。
💡 議会規則改正により、女性議員の産前産後休業が明文化され、政治分野における女性の参画拡大に向けた取り組みが進んでいます。


